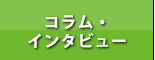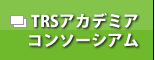コラム・インタビュー

インタビュー第2弾は、『脳トレ』でおなじみの、東北大学加齢医学研究所 所長 川島 隆太 教授です。
約50年も前に現代のAIシステムの発想をしていた川島先生。中学生の頃抱いていた『自分の脳の中身をコンピュータに移植したい!』という夢を叶えるため、東北大学医学部に進学。当時、東京大学医学部教授 伊藤正男先生の「脳の設計図」という本を偶然手にしたことから脳研究への想いは一層広がったそうです。その後、京都大学・スウェーデン カロリンスカ研究所へ留学し、現在は「脳機能イメージング研究」のパイオニアとしてご活躍中です。今回は、脳機能研究の成果やその社会実装、加齢医学研究所の所長としての使命、コロナ禍での脳活動など、興味深いお話を伺いました。
脳科学研究者への夢の第一歩 〜東北大学・京都大学・カロリンスカ研究所〜
―脳の研究といって最初に思い浮かぶのは脳波ですが、先生が医学部に進まれた頃というのは、まだ脳イメージングの研究が走り出したばかりだったのか、あるいはまだその研究もなく脳波の研究が中心だったのか、当時の背景と先生が脳機能イメージングに取り組まれたきっかけを教えてください。
当時、臨床医学で脳波を習ったのですが、よく分からないというのが本音でした。ちょうど東北大学医学部5年生の時に、国立大学では初となるPET装置が導入されました。この装置はガンの早期診断のために導入されたのですが、これを扱っている教授から、応用の仕方によっては人の脳機能・脳活動を画像化出来るかもしれない、という授業を受けました。中学生の頃から、自分の脳機能をコンピュータの中に入れ込んでみたいという夢を持っていた私は『まさにこれだ!』と思って、その装置を扱える大学院の放射線科の研究室に入局しました。ネズミの脳の研究をしても遠回りになる、ヒトの脳機能を直接的に解析してみたいと思っていたのです。
―そういう意味では、非常にタイミング良く東北大学にPETが導入されたということですね。東北大学は当時の脳機能イメージング研究ではトップランナーであった、という認識でよろしいですか?
いいえ、そうでもありません。というのは、私が大学院に入って一番苦労したのが、誰もその装置の扱い方を知らなかった点です。脳研究にどう応用するかということを誰も分からず、宝の持ち腐れになっていました。これでは応用研究には程遠いと思い、京都大学にサルの大脳生理学の勉強をしに内地留学をしました。先人がいなかったので、まずはサルの大脳生理学で行っている実験を人にそのままトレースするところから始めたのです。
―サルで行っていた研究を人に橋渡しするにあたり、色々と大変なご苦労があったと拝察します。特にお困りになった点、工夫された点がありましたら教えてください。
基本的にはニホンザルの脳に電極を差し込み、行動を学習させて、その時のニューロン活動をシングルユニットで記録する、という類の大脳生理学をやってきました。その手法を人に応用する際に考える必要があったのは、課題の組み方と問題意識の持ち方でした。実際にサルで行った実験と全く同じ様な実験を、ヒトの脳イメージングで応用したのは、私が師事した京都大学霊長類研究所の久保田競先生が考案したGo/No-go課題の実験です。何かを行動するか、あるいは我慢して抑制するか、という単純な課題なのですが、Go=行動するという脳活動と、行動の準備はするが実際には行動を発現しない、という抑制の部分とを分けて解析するということが生理学領域では主に行われていて、それをそのまま人に応用してみたのです。実はGoの時とNo-goの時とでは、ヒトでもサルと同様に全く違うプロセスを経る、ということを明らかにすることに成功しています。ただ、大きな苦労はありませんでしたが、難しいと考えたのは、サルが出来ることには限界があり、かつ自発運動といいながら殆ど条件反射という点です。ヒトの場合は本来の自発的な運動・行動が中心になりますので、同じアプローチ手法では自ずと限界があると感じました。PET等の脳機能イメージングを使った生理学を展開しようと思っていたのですが、既存の学問のラインから全く外れたことをしてしまうと相手にされないだろうという思いがありました。当時サルの大脳生理学も最先端の研究でしたので、先ずはそれとパラレルな成果を出し、方法論的にも間違いはないということを知らしめた上で、ヒトならではの脳機能研究に入っていこうという戦略をとりました。
―カロリンスカ研究所へ留学された経緯と研究内容・成果について、お聞かせください。
 京都大学大学院在学中に、スウェーデンのカロリンスカ研究所では既に同じ装置を使って脳機能のマッピングに関する論文化まで成功していることを聞き、非常に焦りました。すぐにその論文を出した教授宛に手紙を書き、大学院修了後にカロリンスカ大学に留学をすることになりました。そこから本格的にマッピングの勉強が始まったという感じです。
京都大学大学院在学中に、スウェーデンのカロリンスカ研究所では既に同じ装置を使って脳機能のマッピングに関する論文化まで成功していることを聞き、非常に焦りました。すぐにその論文を出した教授宛に手紙を書き、大学院修了後にカロリンスカ大学に留学をすることになりました。そこから本格的にマッピングの勉強が始まったという感じです。
私が師事したのはPETを使って脳のマッピング研究をしておられた、ペル ローランド先生というデンマーク人の教授です。構成員は、教授1名、あとは留学生が主体でその下に大学院生がいるという教室でしたから、最初から研究の主力としてPETを使った研究を行うことができました。
ローランド先生が神経内科医、特に体性感覚/触覚の専門家でしたので、触覚に関する脳研究のお手伝いをしながら自分なりのオリジナル研究が何か出来ないかと日々考えていました。私が行った二つの大きな仕事として、一つは運動における空間認知の研究、もう一つは物事に集中した時、集中する領域が活動する代償としてその集中を妨げる感覚の領域の抑制がかかるということを発見した研究です。
川島研究室の活動
―現在川島研究室では、脳機能イメージング、脳機能開発研究、認知症予防の3本柱で研究を遂行されていらっしゃいますが、今イチオシの研究テーマがありましたら、ご紹介いただけますでしょうか。
基本的にはメインの仕事は脳機能のマッピング研究になります。![]() 川島研究室ではfMRIや脳磁計(Magnetoencephalography - MEG) など、ありとあらゆる脳のイメージング装置を所持、活用しており、世界的にも稀有な研究環境を作ることに成功しております。それらをフルに使って脳活動、脳機能のマッピング研究を行っています。
川島研究室ではfMRIや脳磁計(Magnetoencephalography - MEG) など、ありとあらゆる脳のイメージング装置を所持、活用しており、世界的にも稀有な研究環境を作ることに成功しております。それらをフルに使って脳活動、脳機能のマッピング研究を行っています。
私が脳機能マッピング研究を(日本に)持ち込んだ1980年後半〜1990年代初頃は結構ダイナミズムがあって、研究をすればするほど色んな新しい知識が得られたという状況でしたが、2000年代からは原理のゲの字も知らない研究者達が装置だけ使って計測するということをやりだしてきて、非常に微細な脳活動の違いについて画像化を試みる、という方向になってきました。私達はダイナミズムの中で一番面白い部分の研究をしてきたので、もちろん、チームとしては微細な差を描出するような研究も行っていますが、最近の流れに関しては面白みを感じず、私自身の興味としては薄れてきてしまいました・・・。
もう一つの大きなチームは、子供の脳発達の研究チームです。こちらは社会的な使命を果たそうと思ってやっています。こちらのチームの目標は、健常に発達している子供達でも、様々な認知機能発達障害のある子供達でも、生活習慣の中に脳機能が改善するヒントがあるのではないかという仮説をもとに疫学研究を展開しております。こちらの研究では多くの成果が出てきており、世の中に情報として還元することに成功しております。また高齢者に関しても、認知的介入を行って、人々の認知機能が上がるということの証明が終了し、アメリカの企業による社会実装が始まっていますので、あとは現場でより良いものに育っていってくれればと思っています。
私の方針としましては、大学院の学生やスタッフ達に関しては自分達の興味・関心の方向性に沿った研究を組み立てるように指導しております。研究室として纏まった方向性は何か?と問われると、それはバラバラです(笑)。私がやりたい事を無理にやらせたのでは、学生達は研究者として成長しませんので、自分の興味のある事に関して実験をして、結果を得て、それを発表することをモチベーションとして育ってほしい、という願いを込めて指導しています。
研究者の反省点からスタート 株式会社NeU
―NeUの設立の経緯や、どのような事業を展開しているのかお聞かせください。
簡便な脳機能計測装置を開発し、日常生活での脳の働きをモニターできるようにすること、そしてその装置で脳の働きをモニタリングしながら脳をトレーニングするという新しいサービスを提供することが![]() (株)NeUの大きな事業目的です。
(株)NeUの大きな事業目的です。
実はこの会社の原点は、我々研究者の反省から始まっています。これまでは、脳機能のマッピング研究といっても、物凄く特殊な環境の中でしかヒトの脳の働きについては調べられなかったのです。MRI、PET装置にしても、ガントリーの中に被験者を寝かせておいて、装置の制限の中で与えられる刺激を与えて、極めて限られた反応をさせて、脳のどの部分が働いた、という事しか分からない。我々生きている人間を考えた時に、また私自身の夢である『自分の脳をコンピュータの中に入れよう』と思った時に、本当にそのデータが有効なのかという疑問を抱きながら実験していました。そういった経緯から、日常生活の中での脳の活動の意味をきちんとデコーディングすることが出来ないかと考えるに至り、この思いを実現させるために簡便な脳機能計測装置の開発に乗り出したわけです。
NeUのもう一つの大きな事業として脳トレーニングのサービスを提供していますが、これも大学で行ってきた研究の反省点に起因しています。例えば、きちんとした統計学に基づき、認知症の高齢者の方に認知介入をして症状が改善した、という確固たるデータが出たとします。学者としてはこれで100点です。ところが個別のデータを見ていくと統計学的に有意な改善といっても、必ず10%〜15%の人がドロップアウトした上での『統計学的有意差』になっているわけです。マスとしてみれば我々学者の使命は果たしているのですが、それを社会システムに適用していった場合、受け手個人としてみると、その外れた15%の人にとっては全く役に立つトレーニングになっていないことになります。そこで、サービスとして提供すると考えたとき、15%のロスを無くすにはどうしたら良いかと考え、 “予測”というタイプの研究を開始しました。これは割と新しいタイプの研究になります。すなわちトレーニングをしている時の環境、またどのようなトレーニングをすると良い結果が出るという予測が出来るかを縦断的に追いかけて行って、最終的には最初の状態でどのようにすれば脱落なくトレーニングすることが出来るか、を解明する研究です。 例えば、結論の一つとして出たのが、右利きの人では左半球の背外側前頭前野のエリアを狙ったトレーニングを行うのですが、この脳領域を使う頻度の多い人であればあるほど効果は高い。逆にそこを使っていない人達はトレーニング後も効果が上がらないということを見つけ出しました。話は単純で、トレーニング中にそのエリアの脳活動をモニターすれば良く、そこを使うようにトレーニングをすれば、ドロップアウトせずに脳を鍛えることができます。しかしながら大学研究のように大きな資金を投じればMRIを使ってモニター出来ますが、社会のコストを考えると実生活ではMRIを使ってモニターすることは出来ません。社会実装を考えた時、誰でも自分の脳活動を計測できなくてはいけない、ということで株式会社日立ハイテクと一緒に着手した簡便な脳機能計測装置が脳トレーニング事業にはなくてはならないのです。
例えば、結論の一つとして出たのが、右利きの人では左半球の背外側前頭前野のエリアを狙ったトレーニングを行うのですが、この脳領域を使う頻度の多い人であればあるほど効果は高い。逆にそこを使っていない人達はトレーニング後も効果が上がらないということを見つけ出しました。話は単純で、トレーニング中にそのエリアの脳活動をモニターすれば良く、そこを使うようにトレーニングをすれば、ドロップアウトせずに脳を鍛えることができます。しかしながら大学研究のように大きな資金を投じればMRIを使ってモニター出来ますが、社会のコストを考えると実生活ではMRIを使ってモニターすることは出来ません。社会実装を考えた時、誰でも自分の脳活動を計測できなくてはいけない、ということで株式会社日立ハイテクと一緒に着手した簡便な脳機能計測装置が脳トレーニング事業にはなくてはならないのです。
―NeUの活動は、川島研究室の中心になりつつありますか?
社会実装に関わるような活動は、研究室のスタッフにはやらせていません。将来的にこの仕事で生計を立てられるか未知ですし、学生には「学問」に専念してもらいたいので。NeUはあくまでも私個人の興味の矛先として、基礎研究の成果を社会に役立てる、実装するというところにエフォートを注いでいます。
―NeUが開発した脳機能計測装置により得たデータは、個人だけのデータとして活用しますか?それとも装置を使用した人たち全体のデータとして活用しますか?
これは現在のビッグデータの考え方と同じように考えています。遺伝子情報等も含めて本来は個人に帰属すべき元々のデータをマスとして収集することによって、より社会に有益な新しい情報が出るに違いないということで、全員からデータを集められるようにしてあります。
今、市場としては日本が中心ですが、中国からアジア圏を中心に動き出しています。アジア圏の主な興味は子供の教育です。より効率的な勉強の仕方を知りたい、またより勉強ができる脳を作りたいというリクエストがあって、それに対しても応えています。高齢化社会を迎える危機感を抱いている国、日本・台湾・中国本土は20年後くらいに超高齢化社会に突入しますので、高齢者対策も並行してターゲットとしてやっています。一方でホワイトカラーを中心とした壮年層に対するデータ取りは、今は日本を中心に行っています。
―例えば、発達障害があるような子供に対して、現在開発されている機器を用いた脳機能の評価系というのがどのように役に立つとお考えですか?
発達障害は非常に多彩で、100人いれば100通りの症状があるので、必ずしもきちんとした「方程式」が書けるかというと難しいところですが、認知機能トレーニングにより認知機能が上がっていくだけでなく、社会性を得ることができるという研究結果が出ています。特にADHD系の子供達に関しては、スマホやゲームのようなガジェットを使うことを気に入ってくれるので、認知的介入としては有効だと思っています。でも、サービスの提供には時期尚早だと思っています。発達障害のお子さんをお持ちの保護者の方々は、藁をも掴む思いで何にでも手を出してしまう行動傾向があって、そのような中に開発したものを投入すると、奪い合うように手に取ってもらえることは分かっているのですが、それは私が望んでいる社会実装とはちょっと違っています。きちんとエビデンスを出し、個別化の情報を出せるところまで成熟させてから、提供していきたいと思っています。
―日立ハイテクの開発した光トポグラフィ(NIRS)の技術について伺います。頭骸骨の内部の血流変動をこの光トポグラフィでどの程度精密に検出できるのでしょうか?先生の目から見て、この測定器が技術的にどれくらい成熟したものなのか、お聞かせください。
![]() NIRSという装置ですが、日本独自の技術で島津製作所と日立製作所が競って研究開発を進めてきました。私自身は、当初その原理を含めて測定器には懐疑的でした。NIRSは、頭の皮膚の表面から近赤外光を照射して脳内に入り、反射してくる光をまた検知するという原理なのですが、光がどこを通過しているのか分からない状況です。近赤外光を用いていますから、オキシヘモグロビン、デオキシヘモグロビンの違う波長の光に吸収されやすい波長の光を入れれば、光の通った領域でのヘモグロビン濃度を測れるということは論理的には理解できるのですが、それが本当に脳活動とどの様に関係があるかは大いに疑問に感じられました。そこで、正式に研究に採用する前にfMRI等を使って同じ被験者で同じ実験系を走らせて、少なくとも脳表面に関しては見たいデータとfMRIのデータが一致するという検証は自分達で行いました。そしてその結果、驚いたことに両者には然程違いはないということが証明されました。つまり、いきなりNIRSの研究を行ったわけではなく、必ずfMRI等を使ったマッピングによりターゲットを決めたうえで、研究を進めていったわけです。NIRSをデコーディングのツールとして検証するけれども、フォーカスするエリアは必ず精緻なイメージングを使って決める、というルールの元で開発してきたのです。
NIRSという装置ですが、日本独自の技術で島津製作所と日立製作所が競って研究開発を進めてきました。私自身は、当初その原理を含めて測定器には懐疑的でした。NIRSは、頭の皮膚の表面から近赤外光を照射して脳内に入り、反射してくる光をまた検知するという原理なのですが、光がどこを通過しているのか分からない状況です。近赤外光を用いていますから、オキシヘモグロビン、デオキシヘモグロビンの違う波長の光に吸収されやすい波長の光を入れれば、光の通った領域でのヘモグロビン濃度を測れるということは論理的には理解できるのですが、それが本当に脳活動とどの様に関係があるかは大いに疑問に感じられました。そこで、正式に研究に採用する前にfMRI等を使って同じ被験者で同じ実験系を走らせて、少なくとも脳表面に関しては見たいデータとfMRIのデータが一致するという検証は自分達で行いました。そしてその結果、驚いたことに両者には然程違いはないということが証明されました。つまり、いきなりNIRSの研究を行ったわけではなく、必ずfMRI等を使ったマッピングによりターゲットを決めたうえで、研究を進めていったわけです。NIRSをデコーディングのツールとして検証するけれども、フォーカスするエリアは必ず精緻なイメージングを使って決める、というルールの元で開発してきたのです。
―その様な検証システムをご自身のラボでお持ちということで、他の追従を許さない素晴らしい体制が整っているということですね。
 余談ですが・・・NIRSだけで判断している研究は、ちょっと信憑性に欠けると思っています。有名なエラーとしては、頭を前に傾けるだけでNIRSのシグナルは変わります。要は首が絞まって顔がうっ血するので血流が増えたように見えてしまうのです。人に何か作業させた時、リラックスしていると首は直立しているのですが、集中してくると前屈します。その動きに合わせて血流が増減するデータが取れるので、何をしても脳が働いたというデータになります。当たり前ですよね(笑)。さらに、某チームの研究結果ですが、寒冷環境にいる時に脳血流が下がるという発表があり、大笑いしてしまいました。寒いと毛細血管は縮まるので皮膚の血流が減少するだけのことなのですが。寒いところで脳血流が下がったらオシマイですよね・・・。
余談ですが・・・NIRSだけで判断している研究は、ちょっと信憑性に欠けると思っています。有名なエラーとしては、頭を前に傾けるだけでNIRSのシグナルは変わります。要は首が絞まって顔がうっ血するので血流が増えたように見えてしまうのです。人に何か作業させた時、リラックスしていると首は直立しているのですが、集中してくると前屈します。その動きに合わせて血流が増減するデータが取れるので、何をしても脳が働いたというデータになります。当たり前ですよね(笑)。さらに、某チームの研究結果ですが、寒冷環境にいる時に脳血流が下がるという発表があり、大笑いしてしまいました。寒いと毛細血管は縮まるので皮膚の血流が減少するだけのことなのですが。寒いところで脳血流が下がったらオシマイですよね・・・。
加齢医学研究所の使命
![]() 加齢医学研究所の前身である抗酸菌病研究所は、結核・ハンセン病を克服するため1941年に創立されましたが、のちにペニシリンの有効性がわかり公衆衛生上の目途が立ったことから、ガンを中心のテーマとして研究を行うようになりました。その後改組し加齢医学研究所となり、ガン研究と共に「エイジングに伴う様々な事象に関する研究」というように研究の範囲を広げた経緯があります。
加齢医学研究所の前身である抗酸菌病研究所は、結核・ハンセン病を克服するため1941年に創立されましたが、のちにペニシリンの有効性がわかり公衆衛生上の目途が立ったことから、ガンを中心のテーマとして研究を行うようになりました。その後改組し加齢医学研究所となり、ガン研究と共に「エイジングに伴う様々な事象に関する研究」というように研究の範囲を広げた経緯があります。
加齢医学研究における定義では、加齢=老化ではありません。加齢とは、生命の誕生から発達、成熟、老化、死に至る時間軸に沿った現象のことです。私が所長に就任した際、超高齢化社会を迎えるにあたって、健康長寿をきちんと支える学問をしていかなければならないと思いました。認知症にターゲットを絞り、分子生物学の分野から臨床まで、一気通貫に認知症予防に関する研究を行うことに方向性を定めて所内の人員を整理してきました。現在、ガンの研究チームが2〜3チーム残っていますが、殆どは認知症予防に繋がる研究を行っています。基礎系の分子生物学系のチームとして、抗酸化に関する研究チームがあります。そこでは、抗酸化の研究を脳の中の微細な炎症を抑えるという部分に発展させて、臨床研究に繋げる研究を行っています。他には細胞老化を研究するチームがあり、単に老化の過程を観るだけではなく、どう老化を制御するかをテーマに研究を行っています。研究の出口としましては、私を含め4チーム体制で認知科学や心理学的な研究をしながら、学内の様々な分野の先生方のお知恵も拝借して、社会実装するための手立てを考えています。
―高齢化社会に伴って認知症に関する研究は非常に進んでいる一方で、寝たきりの状態になると骨格筋や骨など、運動系の研究も非常に重要になると思いますが、中枢神経系の研究と運動機能に関するエイジングの研究というのはこれから益々融合して発展させていくことが重要だと感じました。
同感です。この様な研究の最終段階の主流は何かというと、マルチドメインの介入といわれています。運動と認知だけでは無くて、日常生活に関する介入、そして最近始まりだしたスリープテック(睡眠)の介入を組み合わせながら、全体として人々の健康長寿を支えていくという方向に研究は進んでいます。弊所も脳の認知機能を確認しながら、マルチドメインの研究は初めています。
―細胞老化と脳の微細な炎症応答の関係、そして抗酸化に関する研究の話しがでてきましたが、アルツハイマー病はかつて神経病として扱われていましたが、最近ではその考え方も少しずつ変化し、循環器病、すなわち微小循環障害に着目した研究が増えてきました。
そうですね。我々は、微小循環障害が起こる更にその根の部分として、慢性炎症に注目をしています。慢性炎症の主な原因の一つが抗酸化作用だろうと考え研究を進めています。慢性炎症の次の影響として血管系にも影響が出るのではないかと考えます。
―ところで、先生がこれまで構築されてきた脳マッピング解析ですが、今後は脳のどのような部位や機能に着目して研究を進めていきたいとお考えですか?やはり、海馬とかを中心に見ていくということでしょうか?
もちろん古典的な研究は海馬がターゲットですが、私達はやはり大脳皮質にも興味があります。ただヒトのマッピングでは分からないので、私のチームは動物用のMRI装置を持っていますので、ヒトのイメージングで出た結果を模倣して逆にマウスやラットを使って同じようなイメージング結果を得られるような実験系を作り、ヒトの脳で何が起こっているのかを推測するタイプの研究も並行して進めています。
―いわゆるモデル動物を作製していくということですね。
そうですね。モデル動物と人と同じMRIという装置で、同じような課題中の脳活動まで計って、かつ同じようなエイジングのモデルも立てています。私のマウスやラットは今脳トレしたり筋トレしたりしていますけれども、ヒトで試みようとしている事をマウスやラットにやってもらい脳内変化などを調べてヒトの結果を推測するという実験系を作っています。
―我々動物科学を専門にしている獣医にとっては、大変面白いお話で、先生と何か夢のあるような研究をご一緒出来ないかと思ってきたところです。
そろそろ、お時間も迫ってきましたが・・・
昨今のコロナ禍、今後は新たな生活様式に順応していかなければなりません。先生が今までやってこられた研究をWith Corona / After Corona にどの様な方向性で活用できるか、あるいはコロナに関連する新しいテーマの研究をスタートするなど、何かお考えがありますでしょうか。
もう既にいくつか始めています。例えばリアルなFace to Faceのコミュニケーションと、この様なウェブベースでのコミュニケーションというのは、人間の脳にどう関係してくるかという研究を開始しています。この研究により、人間の脳の中でも背内側前頭前野-額の中央の部分に、他者の気持ちを思いやるという領域の脳活動の血流の揺らぎが、コミュニケーションが良好の状態だと同期するという現象を発見しました。コミュニケーションが上手くいかないと同期しなくなります。実際に学校の授業中の脳活動も計測していて、上手な授業の時には、生徒と教師、生徒と生徒間の脳活動が同期するというデータもとれています。現在は、リアルタイムコミュニケーションとオンラインコミュニケーションで脳活動の同期がどの程度現れるのかについて、論文を執筆中です。
―先生の手法を使って、個人の脳機能を改善するだけではなく、他者とのコミュニケーションの質を科学的に知ることが出来るということですね。逆に、人との良好な関係性を築くにはどうしたら良いかのヒントになりますね。
はい、その辺の研究は大変面白いと思います。どこまでやれば人の脳は騙されてリアルなコミュニケーションが担保されるのかは、これから脳科学によって世の中に提供できるのではないかと思っています。
また鬱的な症状を改善するためにどういう生活習慣をさせると効果的か、というようなことは疫学研究の分野では既に始まっています。あとは孤独感を感じている人の脳の状態がどうなっているかについても、イメージング研究からスタートして、既に結果も出ていますので、社会実装に向け介入の可能性についてすでに検討段階です。そういう意味では、当ラボでは、脳科学の観点から With Corona / After Corona に対する研究を積極的に行っていると言えるでしょう。
―今後はAIが社会の主流となってきて、全部が機械任せという部分も出てくると思います。素人的に考えると、AIの発達と脳機能というのは相反してしまうのではないかという恐ろしい想像をするのですが、人間の持つ素晴らしい脳機能を低下させないために、AIの機能を上手く活用するという方法はありますでしょうか。逆に、AIの発達による脳機能への危険性などについて、どの様にお考えでしょうか。
 そのような問題については、常に考えています。弊所には、仙台市の全ての公立小・中・高校に通っている子供の学力のデータから生活習慣データまでが揃っていまして、スマートフォンやIT機器の利用が子供達の行動にどういう影響を与えるかについて調査研究を行っています。結果、こうした機器の使用頻度の高い子供は色々なものを失っている、というデータが既に出ていまして、スマートフォンに依存傾向がある場合、大脳白質に老化のサインが綺麗に出ていますので、“脳の退化”が起こっていると言えるでしょう。
そのような問題については、常に考えています。弊所には、仙台市の全ての公立小・中・高校に通っている子供の学力のデータから生活習慣データまでが揃っていまして、スマートフォンやIT機器の利用が子供達の行動にどういう影響を与えるかについて調査研究を行っています。結果、こうした機器の使用頻度の高い子供は色々なものを失っている、というデータが既に出ていまして、スマートフォンに依存傾向がある場合、大脳白質に老化のサインが綺麗に出ていますので、“脳の退化”が起こっていると言えるでしょう。
―AIを専門にする研究者達も良い事ばかり言わないで、脳機能研究をしている先生方とジョイントしてAIのリスクについても積極的に科学でアピールしていってほしいと思います。
同感です。どういう未来構図のもと研究されているのか、是非聞いてみたいです。人がものを考えなくて良くなるなら、人は何?という話になるわけですから。遺伝子工学がもっと発展していくと子供を作るのも、別にリアルな人はいらなくなりますよね。要は遺伝子を残すために我々の肉体がいらなくなったら、存在が無意味になってしまいます。
これから我々の文明をどういう方向に発展させるかを決めるのは我々自身ですが・・・。
どこかに移動する場合、自分の体を使わなくても移動可能な手段にお金を出すことをしたが故に、我々の基礎体力は下がっている。それを代償するためにジムに通うコストをかけています。脳に関しても同じと考えていて、人間自身が考えることをしなくなっていくでしょう、でも人が人としてあるためにジムに通う感覚で認知機能のトレーニングをするという未来になっていくのかなと思っています。
―最後に、これからの若手研究者に向けて、期待していることはありますでしょうか。
研究のダイナミズムが非常に失われてきていると思います。大きな流れの中のどこかのパーツを研究していると思っている研究者が多いと思います。研究の成熟に伴ってそうなってしまうのは分かりますが、その様な中でも大きくダイナミズムを感じられる領域は必ず見つかると思います。歯車の一部として研究するのではなく、自分で歯車を作るのだという気概をもって視野を広くもってもらいたい、というのが私からの願いです。
※1:2017年8月 東北大学加齢医学研究所 川島研究室の「認知脳科学知見」と、日立ハイテクの「携帯型脳計測技術」を融合して、株式会社「NeU(ニュー)」が設立されました。
『脳科学でQuality of Lifeの向上に貢献する』をミッションに掲げ、脳トレから脳活動を計測する簡便な装置に至るまで、幅広い脳科学ソリューションを展開しています。
編集後記:
先生のお話を伺い、改めて自分自身の研究や生活の習慣を見直す絶好のチャンスをいただきました。そして、現代はスマホやPCに頼りがちですが、つい最近まであたり前のように行っていた、「読む・書く」という行動がいかに脳にとって重要か、自らの体を動かす「歩く」ことがどんなに大切かを痛感いたしました。
便利さを追求したがゆえに、人間の存在意義が危ぶまれる世の中・・・これからの時代をどう生きていくか、一人一人が脳をフル稼働させてより良い社会の今後をイメージしていかなければなりません。
(2020年11月吉日)